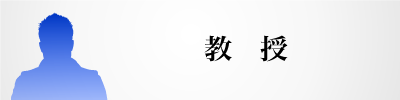今年も厳しい年でしたが、2025年はもっと厳しい年になる理由がいくつかあります。
2007年が電子マネー元年と呼ばれていますが、2018年にPayPayの提供が始まってからが本格的な電子マネー時代だといえます。
それから約6年が経過しています。
キャッシュレス決済比率は年々上昇を続け、2024年3月の政府発表では39.3%(126.7兆円)です。
今後も利用は伸び続けることは間違いありません。
全ての年代で「キャッシュレスで払いたい」という比率が7割を超えました。
全 体 57.6%
20代 56.2%
30代 63.7 %
40代 59.8 %
50代 57.9 %
60代 59.8 %
70代以上 54.3%
※出典:Marke Zineニュース
もはや若年層の電子マネーではなく、国民の電子マネーに近づきつつあるのです。
このままキャッシュレス決済が2030年まで対応不可となる産業など、お客様が離れてしまうことは避けられません。
電子マネーには次の2点の特徴があります。
・顧客の囲い込み
今後人口減少でパイが小さくなる中、今のうちにどれだけお客をつかめるかかが生き残りのカギとなるからです。
・究極の顧客情報
従来のPOSシステムより格段に精度の高い情報を蓄積し、商品戦略や宣伝活動に結びつけられるからです。
これらの理由からも、10年後に対応すれば良いという考えは危険だといえます。
特にパチンコは、10代から20代に遊技を始めなかった人が、その後30代以降から遊技を始める可能性が著しく低いからです。
これに10年間も対応が遅れれば、業界にとって致命傷になるのは明らかです。
このインフラ整備が遅れれば、参加人口の減少に歯止めがかけられないばかりか、加速装置にさえなってしまいます。
設置台数500台規模以下がまだ3,000軒以上あることを考えると、今後6年間平均で毎年350軒が失くなるとしたら、2030年の業界規模は3,900軒にまで縮小する計算になります。
あながちこの店舗数は、ディフォルメされたものではなく、トレンド分析の結果に近いものかもしれません。
危険な問題
(1)まずは、団塊の世代が全員75歳以上になるということです。
すでに2020年から影響は出始めていましたが、コロナ禍がそれを認識しづらくしていました。
その影響はジリジリと強まり、低貸し営業やバラエティー、海などの稼働に現れました。
団塊の世代が後期高齢者となり、参加率が著しく下がるのは当然ですが、問題はそれだけではありません。
団塊の世代の子供達、つまり団塊ジュニアまでの人口数が少ないということなのです。
つまり、団塊の世代から団塊ジュニアまで大きな谷間があるということです。
この部分は凄く重要なのですが、見落とされる部分でもあり、注意が必要な箇所になります。
特に自店商圏において高齢層が多い場合は、ここ数年で稼働数が目に見えて激減する可能性があり、これまでの延長線で営業を考えないことが大切です。
(2)若年層の人数が減り、参加率が落ちている問題です。
人口総数が減り、参加率が減れば、かなり参加人数が減ってしまいます。
しかし若年層は広域で動くため、足場商圏での若年層減少を認識しづらいのです。
若い遊技者が、パチンコやパチスロをしながら携帯を見ている姿をよく見ます。
それほどゲームとしての魅力が無く、ギャンブルとして楽しんでいる証明です。
1つのゲーム開発に対する投資額が違い過ぎること、制作の自由度が違うこと、追加アップデートができること、コミュニティー等があること、無料で遊べることなど、パチンコやパチスロがゲームとして勝てる要因はありません。
20代でパチンコをしなかった人が、その後に遊技をする確率は1%程度なので、今後の30代以下に対して期待は持てません。
(3)消費の中心世代は団塊ジュニアですが、平日の遊技が期待できないことです。
平日仕事をしている世代は、少なくとも3時間以上を必要とする遊技など不可能です。
また、3万円程度のお小遣いが主流の既婚者では、少なくとも3万円以上を必要とする遊技を毎日するなど不可能です。
しかし遊技機のスペックはさらに射幸性を高めて行きます。
粗利率に限界があるなら、売上を伸ばさないと、粗利額は増えないからです。
現在は人件費も広告宣伝費も下がっています。
しかし遊技機の値段は、高くなっています。
この支払いが重荷になって、遊べなくしているのです。
PEST分析の(S)結論
老齢層・中高年・若年層ともに、参加率が減少し続けることが分かります。
足場商圏型の小型・中型店舗
パチンコ市場を構成する店舗数の内、設置台数が500台以下の比率は50%以上あります。
この多くは足場商圏型の店舗であるため、老齢層となった顧客の離反は致命的であり、減少傾向に歯止めはかかりません。
今後5年間も毎年350店舗前後で減少することになりそうです。
若年層の取込み
業界としては若年層の掘り起こしが急務なのですが、現在の打ち手は若者向けのコンテンツ機種開発となっています。
これは同時に、老齢層や中高年層の離反を産んでもいます。
遊技機依存、コンテンツ依存の限界なのかも知れません。
現在は現金を持ち歩かない若年層に対して、電子マネーが使えない状態が続いています。
若年層からパチンコがオールド産業として認識されている主要因にもなっており、新たな参加者を生まない原因にもなっています。
2025年問題への対策
【稼働貢献・売上貢献・利益貢献】
【稼働貢献】
年金生活者は可処分所得が少ない反面、可処分時間はたっぷりあります。
売上貢献や利益貢献にはなり得ませんが、稼働貢献としてならば期待できます。
ただし、あくまでも稼働貢献であるため、営業の主軸に据えることはできませんので、ここにリソースを多く配分することは避けたいところです。
しかし、売上貢献客や利益貢献客の“呼び水効果“とした、割り切った使い方ならば一定の成果を期待できます。
1円パチンコの幅を巧みに利用することで、低貸営業における赤字を少しでも圧縮することは重要だと思います。
【利益貢献】
仕事中心の中高年層の取込みは、ベタなお話で恐縮ですが、土日祝での集客です。
リソースを平日に分散することなく、利益貢献となる顧客に向けて集中配分しなくてはなりません。
次回来店したら、前回遊技した機種が撤去されているを繰り返すと、負けが離反要因になる可能性を強めてしまいます。
利益貢献客としてのターゲットを明確にする場合、年齢だけではなく、個人データからの気質が大切になります。
これなどは特に、アナログ的営業からデジタル的営業へスイッチングすることが急務です。
【売上貢献】
若年層を中心とした広域商圏から集客する重要性です。
特に勝ちを意識したお客様は、デジタル情報から少しでも勝ちやすいお店を選択しようとします。
そのため、参加人数の少ない若年層を集めるには広域からの集客が大切になります。
となるとネット広告やSNSの活用が重要になり、AIDMAの広告原理からAISASへと変わって行くことを理解しなければなりません。
遠方から来店するお客様は、足場のお客様と違って、玉が出ていないから直ぐに帰るというわけにもいかず、単価が高くなる傾向があります。
2025年は、比較的連休が多い年ともいわれています。
ここで中だるみしてしまわないように対策を練ることが必要です。
本年もお世話になりました。
2025年が皆様にとって良いお年となることを願っております。